過活動膀胱に対するボツリヌス療法が保険適応となりました
以前は自費診療で行われていた過活動膀胱に対するボツリヌス療法が2020年4月から新たに保険適応になりました。
ここでは、ボツリヌス治療について詳しく解説していきます。
排尿に関するお悩みはウロギネ科・排尿機能外来へ、お気軽にご相談下さい。
1.過活動膀胱とは?
過活動膀胱とは、「こらえきれない尿意、またそれに伴い尿が漏れてしまう病気」です。過活動膀胱はよく見られる病気で、高齢者であるほど頻度が高く、高齢化社会の日本では現在1000万人以上の患者数がいると推測されています。
過活動膀胱の治療はまず生活指導(水分の取り方、便秘の改善、減量、今飲んでいるお薬の見直しなど)、行動療法(尿意切迫感を少しだけ我慢する)を行い、その後、飲み薬による治療を行います。しかしこれらの治療でよくならない場合があります。
2.ボツリヌス療法とはどんな治療?
ボツリヌス療法とは、過活動膀胱や切迫性尿失禁の患者さんで、通常の薬物療法を行なっても効果が無い、また薬剤の副作用のために治療継続出来ない場合の治療法で、膀胱の筋肉を緩める薬(A型ボツリヌストキシン)を膀胱壁に直接注射する治療です。米国や欧州など世界で広く行われている治療で、日本でも国内の治験を経て2020年4月に健康保険が適応となりました。
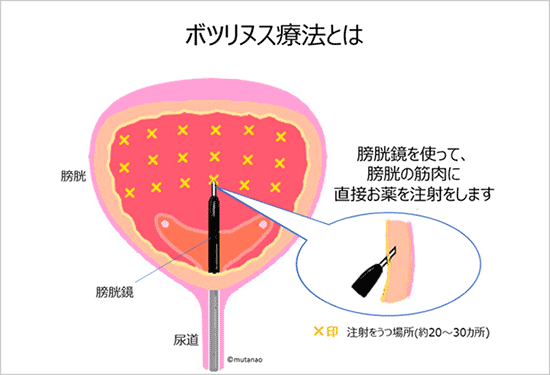
3.治療のメカニズムについて。

過活動膀胱に伴う尿失禁は膀胱の筋肉が異常な収縮を起こすことで起こります。ボツリヌス療法に使用されるA型ボツリヌストキシンは筋肉の収縮を弱める作用があり、この薬剤を膀胱の筋肉に直接注射し膀胱の異常収縮を抑えることで尿失禁を改善させます。(ボツリヌス菌を注射する訳ではありませんのでボツリヌス菌に感染する心配はありません。)過活動膀胱に伴う症状(突然起こる強い尿意、尿失禁、昼間、夜間の頻尿)の改善が期待出来ます。
4.ボツリヌス療法の効果はどれくらい?

治療効果は患者さんによって異なりますが、日本で行われた臨床治験では1日の尿失禁回数が平均で3.6回減少し、27%の患者さんで完全に消失しました。排尿回数に関しては平均で1.7回減少しました(施術6週間後)。治療効果は施術後2-3日で現れ、数ヶ月持続します。時間が経つにつれて薬の効果が減弱して行きます。この場合薬剤を再投与すると同様の効果が現れます。効果がなくなってきたら、あらためて治療が必要になる対症療法です。再投与の時期については医師にご相談下さい。
5.治療についての注意点、副作用は?
- ボツリヌス療法は対処療法であり、薬剤の効果が無くなれば再投与が必要になります。効果の持続は通常4−8ヶ月です。3ケ月未満での再投与は出来ません。
- 投与が繰り返されると徐々に薬剤の効果が薄くなる可能性があります。
- 副作用として、排尿困難(9%)、尿閉(5%)、尿路感染症(5%)、膀胱出血(3%)が観察されています。
尿閉とは、膀胱内に尿が大量に溜まっているのに、尿が全く出せない状態になることを差します。尿閉の場合は自己導尿による対処が必要になります。 - 抗凝固剤を使用されている場合は事前に中止をお願いする場合があります。
- アミノグリコシド系の抗生物質、パーキンソン病の治療薬、筋弛緩薬、精神安定剤などは施術後その効果が強くなる恐れがあります。
- 挙児希望の場合、施術後2回の生理が終了するまで避妊してください。
- アレルギーの出現(発疹、吐き気、息苦しさ)、筋力の低下症状、痙攣等があればすぐに連絡してください。
6.次のような方は、ボツリヌス療法を受けることが出来ません。
ボツリヌス療法を受けられない方
- 未治療の尿路感染症がある方(事前に罹患していないか調べます)
- 残尿があるのに自己導尿などの対処を行なっていない方
- 重症筋無力症などの全身性筋力低下を起こす可能性のある方
- 閉鎖隅角緑内障の方
- 喘息など慢性的な呼吸器疾患のある方
- 妊娠中、授乳中の方
- 施術後の排尿困難が発生した場合に自己導尿に同意出来ない方
受ける際に注意が必要な方
- ボツリヌス治療を受けた経験がある方
- 現在、薬を使用している方(市販品を含む)
上記に当てはまる場合は事前に医師にお知らせ下さい。
7.おひとりで悩まず、まずはお気軽にご相談下さい。
排尿に関するお悩みはウロギネ科・排尿機能外来にて診察が可能です。お気軽にご相談下さい。
(文責:亀田メディカルセンターウロギネ科医師 林篤正、イラスト引用:グラスコ・スミスクライン株式会社)


 このサイトの監修者
このサイトの監修者