窪田先生が肺胞蛋白症に関して勉強会で発表!
当科では毎週木曜の朝に、持ち回りで勉強会を行っており、各医師が興味のある領域についてのレクチャーを抄読会として紹介しています。
今回は、当科医長の窪田先生が、肺胞蛋白症について、朝の勉強会で発表してくれました。
参考文献として、「肺胞蛋白症診療ガイドライン2022」、「European Respiratory Society guidelines for the diagnosis and management of pulmonary alveolar proteinosis.(Eur Respir J. 2024;64(5):2400725. doi:10.1183/13993003.00725-2024. PMID:39147411)」を挙げていただき、特に自己免疫性肺胞蛋白症について、定義、診断方法、画像所見、実際の治療まで概説いただきました。
本邦の疫学調査では、自己免疫性肺胞蛋白症(Autoimmune pulmonary alveolar proteinosis: APAP)の有病率が26.6/人口100万人とされますが、カバーする医療圏の広い当院でも若手を中心に診療経験がない医師もおり、重要な知識の共有ができました。
症状、聴診初見、胸部X線検査、血清バイオマーカーなどにより肺胞蛋白症が疑われる場合に気管支鏡検査を行い、血清抗GM-CSF抗体を測定する、診断アルゴリズムについて説明いただき、2024年12月に保険収載、発売された、血清抗GM-CSF抗体検出キットであるKBMラインチェックAPAPにより、自己免疫性肺胞蛋白症の血清診断が可能となった点についても触れていただきました。
肺胞蛋白症診療ガイドライン2022の「肺胞蛋白症(PAP)画像所見」の項目に記載されているAPAPおよび鑑別疾患のHRCT像を提示いただきましたが、画像のみで診断することが難しく、APAPに典型的とされるcrazy-paving appearanceは、APAPで高頻度に見られるものの、他疾患でも見られる非特異的な所見であることを共有しました。
全肺洗浄、区域洗浄、GM-CSF吸入療法についても概説いただき、科内での診療体制を考える機会になりました。
窪田先生は当科の研修プログラムを卒業後、気管支喘息、COPDを中心とした臨床研究を行うとともに、診療、教育、呼吸器内科運営において、若手医師と中堅医師を繋ぐ重要な役割を担っています。
窪田先生へのインタビュー記事はこちら↓
https://www.kameda.com/pr/pulmonary_medicine/interview_kubota.html

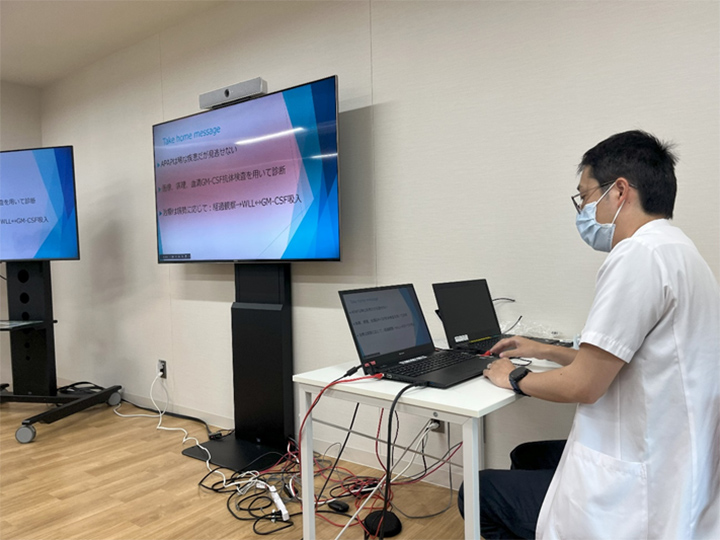
このサイトの監修者
 亀田総合病院
亀田総合病院
呼吸器内科部長 中島 啓
【専門分野】
呼吸器疾患

