第64回日本感染症学会東日本地方会学術集会に青島主任部長、山脇医師、都筑医師が参加。
平成27年10月21日〜23日に札幌で開催された第64回日本感染症学会東日本地方会学術集会に、青島主任部長、山脇医師、都筑医師が参加しました。
青島主任部長は、呼吸器感染症3で座長を担当しました。
山脇医師は「誤嚥性肺炎患者における肺炎球菌抗原検出キットの検出性能についての検討」を発表し、次の結論を述べました。
「誤嚥性肺炎患者においては、ラピラン®肺炎球菌の感度は38%と高くないが、BinaxNOW®肺炎球菌とラピラン®肺炎球菌の特異度は91%、86%でともに高値であった。誤嚥性肺炎患者では、誤嚥によって保菌している肺炎球菌を喀痰培養で検出しているため、偽陽性が多くなると考えられた。」
会場からは、「過去の肺炎や繰り返す肺炎が偽陽性の原因になっていなかったのか?」という質問があり、「過去の肺炎歴などを含めて、偽陽性や偽陰性の原因を検討したが、はっきりしなかった。」と返答しました。
都筑医師は、「急性膿胸に対するウロキナーゼ胸腔内注入療法の後方視的検討」を発表し、「本研究ではウロキナーゼ胸腔内注入療法の有用性が、有意差をもって示されなかった。どのような基準でウロキナーゼを使用したか明確な記載が認められない症例が少なくなく、今後、ウロキナーゼの使用に関しては個々の症例で検討が必要である。」と結論しました。
座長をされた厚生労働省関東甲信越厚生局医療指導官の先生からは「ウロキナーゼの胸腔内注入は保険適応外である。使用してはならないというものではないが、使用するに当たっては根拠を明確にする必要があろう」とコメントを頂きました。
今回の学会は「予防が第一 感染症診療のこれからを考える」というテーマで開催され、感染症学会側の堤裕幸先生(札幌医科大学)と化学療法学会側の坂田宏先生(旭川厚生病院)の両会長はともに小児科が専門とあってワクチンに関する企画が充実していました。3日目にあった会長企画シンポジウムの「新しいワクチン戦略」は小児科の話が主体でしたが、大橋靖雄先生(中央大学理工学部人間総合理工学科生物統計学)による、「ワクチンの効果を考える」の講演では臨床医ではない生物統計の専門家の視点からワクチン研究のデザインや倫理性についてのお話が聴けて、とても勉強になりました。
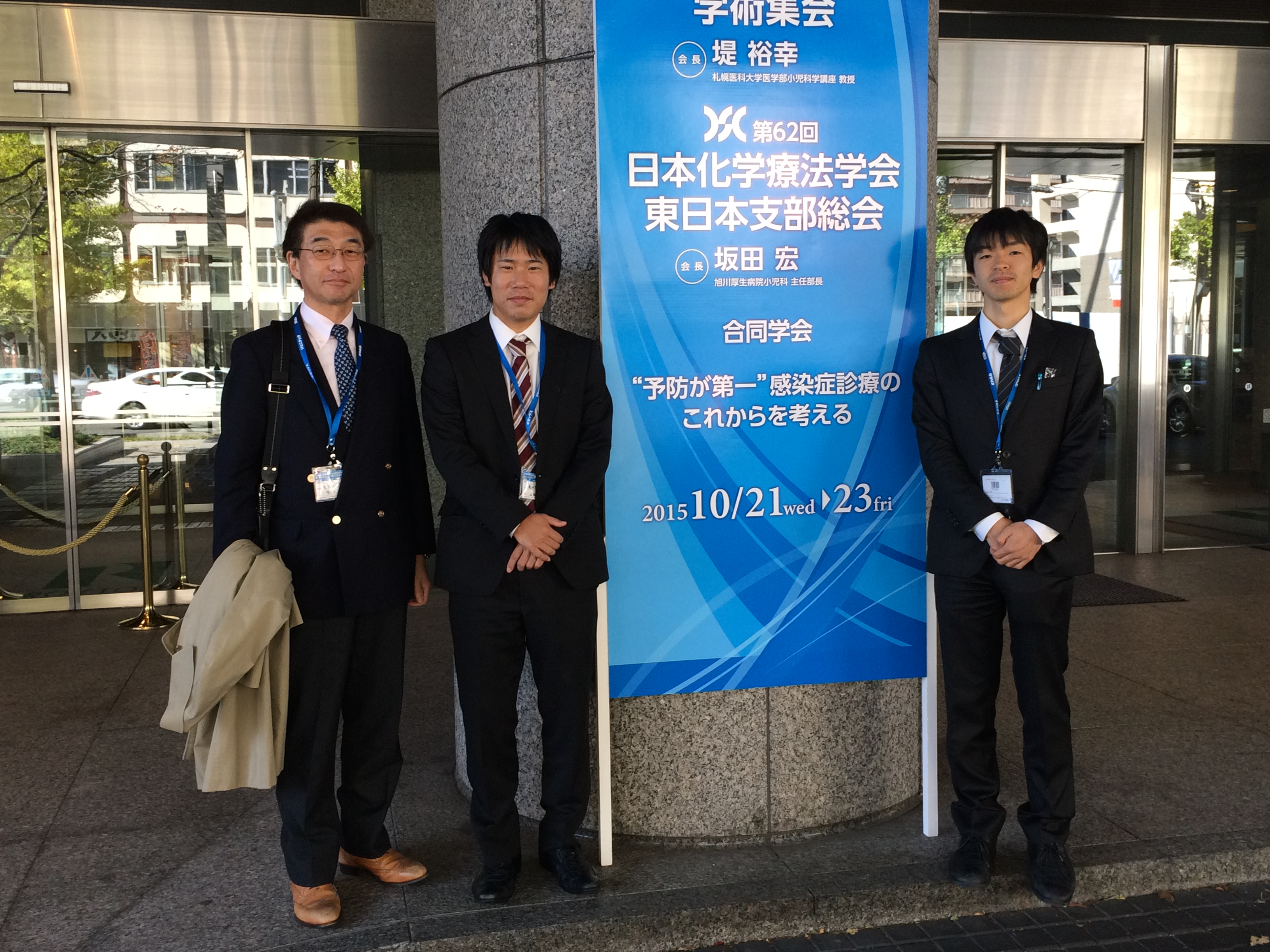
このサイトの監修者
 亀田総合病院
亀田総合病院
呼吸器内科部長 中島 啓
【専門分野】
呼吸器疾患

