坂本先生がGoodpasture症候群について発表!
当科では毎週木曜朝に、各医師が持ち回りで「今注目している領域」について抄読会形式でレクチャーを行っています。
今回は、抗GBM抗体病を経験した当科専攻医の坂本先生が Goodpasture症候群 をテーマに発表してくれました。
Goodpasture症候群とは
Goodpasture症候群は、腎臓の糸球体基底膜(glomerular basement membrane: GBM)および肺胞基底膜(alveolar basement membrane: ABM)に対する自己抗体が原因となり、急速進行性糸球体腎炎や肺胞出血を来す血管炎 です。
1919年にインフルエンザ感染後に肺出血と急速進行性腎炎を呈した症例が報告されたことに由来して命名されました。近年では肺出血を伴わない例も含めて「抗GBM抗体病(anti-GBM disease)」と呼ばれることが多くなっています。
若年(30歳未満)では肺出血を伴うことが多く、50歳以上では腎炎のみで発症する例が多いことが知られています。
本邦の診断基準とガイドライン
日本の診断基準では以下が求められます。
・肺出血と急速進行性糸球体腎炎の存在
・血清抗GBM抗体陽性
・腎生検で糸球体係蹄壁に沿った線状IgG沈着と壊死性半月体形成性腎炎
また、「エビデンスに基づく急速進行性腎炎症候群(RPGN)診療ガイドライン2020」では、抗GBM抗体価の高さが腎予後不良因子であることが強調されています(血清Cre≧6.78mg/dL、無尿、正常糸球体の欠如、全周性半月体優位と並ぶ因子)。
治療と特殊な病型
標準治療は
・血漿交換療法
・プレドニゾロン
・シクロホスファミド
が中心です。近年では、エビデンスは十分でないもののリツキシマブやミコフェノール酸モフェチルの使用も報告されています。
また、特殊型として
・ANCA陽性例
・膜性腎症合併例
・IgG4抗GBM抗体型
についても紹介されました。
発表後の議論では、「急激な腎機能障害を来す疾患のひとつとして常に念頭に置くべき」「尿検査やANCA・GBM抗体測定の重要性」など、日常診療での注意点について意見が交わされました。
坂本先生は3カ月間の地域研修を経て7月から当科に復帰しています。臨床研究にも取り組み始めており、今後の活躍が期待される若手医師です。
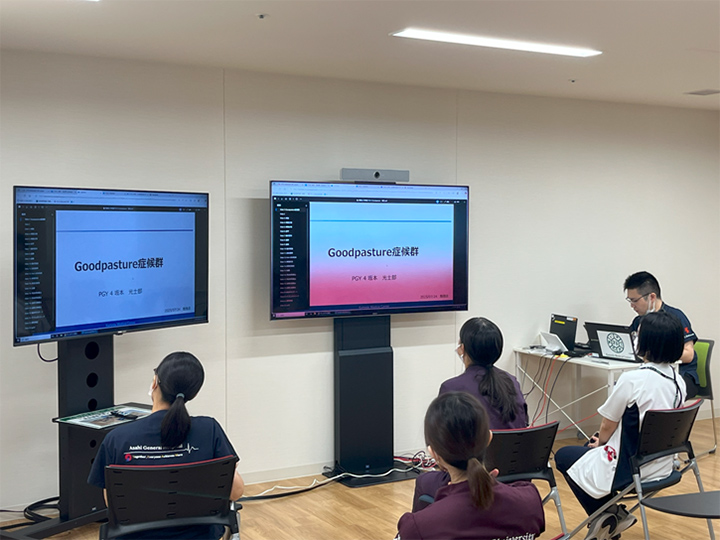
このサイトの監修者
 亀田総合病院
亀田総合病院
呼吸器内科部長 中島 啓
【専門分野】
呼吸器疾患

