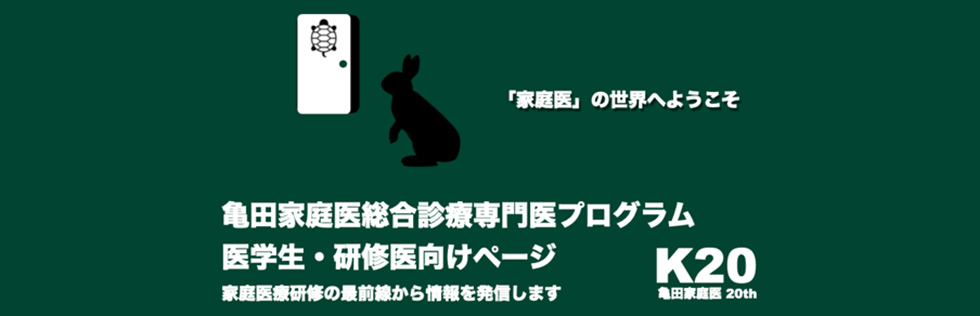米国における多疾患罹患有病率の傾向: 1988年〜2014年(第7回RJC)
ジャーナルクラブ 第7回
2018/07/26
高橋亮太
1 タイトル
「米国における多疾患罹患有病率の傾向: 1988年〜2014年」
Multimorbidity Trends in United States Adults, 1988-2014.
Dana E. King, Jun Xiang, and Courtney S. Pilkerton.
J Am Board Fam Med July-August 2018 31:503-513; doi:10.3122/jabfm.2018.04.180008.
カテゴリー research journal club
キーワード 横断研究 ヘルスケア費用 医療政策 多疾患罹患 栄養調査 有病率
プライマリヘルスケア 社会経済的因子
2 背景・目的・仮説
●背景
多疾患罹患(multimorbidity)は「1人の患者において慢性疾患を2つ以上保有する状態」と定義され、プライマリケアの重要な課題
これまでの研究においては、高齢者人口のみを対象としている、慢性疾患(状態)個数が限定されている、慢性疾患(状態)に肥満を含めていない研究が多かった
肥満が含まれていないことにより、有病率が過小評価されていた可能性が否定できない
多疾患罹患による疾病負担(disease burden)として、死亡率の増加と関連することがメタアナリシス等で示されている
●目的
肥満を含む11個の慢性疾患(状態)で現在の多疾患罹患有病率を検討すること
この25年間での有病率傾向を検討すること
年齢、性別、人種、社会経済的因子等の関連要因について検討すること
3 方法 研究デザイン
●研究デザイン
横断研究(横断研究データを複数年分使用して比較するデザイン)
●研究母集団
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES)
serial, cross-sectional, stratified, multistage probability survey
米国市民 施設入所していない人々
National Center for Health Statistics(NCHSはCDCの一部門)が実施
実施方法 インタビュー+身体計測+臨床検査
> 詳細は、https://www.cdc.gov/nchs/nhanes/about_nhanes.htmを参照
●研究対象者
20歳以上成人 57,303人
1)NHANES III 16,573人(1988-1994年)
※6年間で1回分の調査
2)NHANES 1999-2014 40,730人(1999-2000, 2001-2002, ---, 2013-2014年)
※2年間で1回分の調査
●多疾患罹患(multimorbidity)
多疾患罹患の定義 1人において2つ以上の慢性疾患(状態)を保有する状態
基本的には自己申告(一部、身体計測データ、臨床検査データを併用)
「これまでに医師から下記の疾患(状態)と伝えられたことがありますか?」
11の慢性疾患(状態)
> 1.心血管疾患(うっ血性心不全、冠動脈疾患、心臓発作)
2.COPD(肺気腫、慢性気管支炎)、3.CKD(eGFR<60)、4.気管支喘息、
5.関節炎、6.癌、7.脳卒中、8.高血圧(自己申告 or sBP>140 or dBP>90)、
9.高脂血症(自己申告 or T-cho>200)、10.糖尿病(自己申告 or A1c>6.5)、
11.肥満(自己申告 or BMI>30)
★この研究のプライマリアウトカムと設定
●共変量(説明変数)
年齢(3群:20-44, 45-64, 65+)
性別(男性、女性)
人種(4群:非ヒスパニック白人、非ヒスパニック黒人、ヒスパニック、その他)
教育歴(高校卒業以上、高校卒業未満)
家計収入(貧困状態以上、貧困状態未満)
健康保険(加入している or 加入していない)
●統計解析
記述疫学
傾向性の分析
ロジスティック回帰分析
4 結果
(表1)多疾患罹患有病率の人口統計学的な特徴
年齢群別 性別 人種別 教育歴 健康保険
59.6%(2以上)2014年 ← 45.7%(2以上)1988年
38.5%(3以上)、22.7%(4以上) 2014年
(表2)多疾患罹患有病率(2以上)の1988年〜2014年までの経時的変化
(表3)多疾患罹患有病率(3以上)の1988年〜2014年までの経時的変化
(表4)多疾患罹患有病率(4以上)の1988年〜2014年までの経時的変化
(図1)上記の表2〜4の結果をグラフに整理したもの
(図2)個別の慢性疾患(状態)ごとの1988年〜2014年までの経時的変化
>肥満 54.1% 2014年 ← 41.9% 1988年
統計学的に有意な増加傾向を示した
5 考察
●全体のまとめ
米国における多疾患罹患有病率の高さと増加傾向がみられた
20歳以上成人において半数以上(59.6%)であり、1988年と比較して高値
65歳以上は91.8%とさらに高値 男性より女性がやや高め
●過去の研究との検討
National Health Interview Survey (ref.30)
CDCデータ(ref.31)
Medicare(ref.32)
今回の研究は肥満を慢性疾患(状態)に入れたことで有病率がさらに増加したことが考えられる 肥満は多くの重要な疾患の病理学的プロセスや危険因子に関連する
今後も多疾患罹患の研究において、慢性疾患(状態)の一つとして入れるべきではないかと考える
●多疾患罹患有病率の増加要因に関する考察
多疾患罹患有病率が増加している要因について、過去の研究では
Princeら(ref.36)の研究では世界的な問題で流行(epidemic)となっている
不健康な食事パターン、運動習慣の欠如、喫煙、社会経済的要因等の影響が要因として検討されている。その他の理由として、プライマリケアへのアクセスが容易になったことで診断が増えたのではないかとする研究もあった。
本研究においては、多疾患罹患有病率増加の背景には、肥満者の有意な増加による影響があると考えられた。
●限界
誤分類(misclassification)の可能性 > 多疾患罹患が自己申告に基づくもの
データの一貫性の問題(25年間に渡る長期データであること)
慢性疾患(状態)が限定されている。特に精神疾患(うつ、不安、オピオイド中毒等)が含まれていない。
横断研究データであり、それぞれの年次の集団は、他の調査時点とは別の集団であり、一貫性がないこと
●まとめ
11の慢性疾患(状態)をもとにした多疾患罹患有病率を検討した
高い有病率であり25年間で増加傾向を認めた
この傾向に肥満が関連している可能性が考えられる
今後どのような介入方法がこの多疾患罹患集団に対して有効となるかの研究が期待される
6 日本のプライマリケアへの意味
●アメリカ
25年間で多疾患罹患有病率が増加
その背景に肥満増加が一因として考えられている
●日本
肥満者が増加傾向あり
> 日本においても多疾患罹患に関する研究の必要性が高まっている
以上
このサイトの監修者
 亀田ファミリークリニック館山
亀田ファミリークリニック館山
院長 岡田 唯男
【専門分野】
家庭医療学、公衆衛生学、指導医養成、マタニティケア、慢性疾患、健康増進、プライマリケア・スポーツ医学