1ヶ月ローテート報告:家庭医療専攻医Sr2 篠崎先生
在宅診療部は新年度もローテートの先生と一緒に学びを続けております!
5月は篠崎先生がローテートしていただき、その感想をいただきました。
熱心に&貪欲に学習していました。KFCTでの在宅医療でも存分に力を発揮してください!
〜〜〜
1か月間、在宅診療科のローテーションをさせていただきました。
短い期間といえども、1か月間継続して同じ地域の在宅の患者さんに関わらせていただくことで、新しい気付きを得ることができました。
1か月間通して在宅診療で難しいなと感じたと同時に、やりがいのある側面であると実感したことを述べていきます。
まず1つ目は、癌終末期の患者さんの診療です。癌終末期の患者さんに対しては、素早い病態の把握と症状緩和の対応が求められ、同時に本人と家族の心理的なサポートを行い、自宅の介護環境の調整を他職種で連携して整えていく必要があります。
次に、安定している在宅の患者さんが突如具合が悪くなる時です。慢性疾患で長く在宅診療を利用していた患者様が、あることをきっかけに救急搬送、入院が必要かどうかの決断に迫られることがあります。問診と身体所見、採血、エコーなど、自宅でできる範囲の検査で診断をしていかなければいけません。そのまま自宅で治療可能なケースもありますが、そのためには自宅で継続して診ることができる環境なのか、今までの本人家族の病体験や家族の状況など様々なことが影響しています。そういったことを踏まえて病院に搬送するかどうかとても悩むところだと思いました。
一方で、在宅で診療を行うことでいいなと感じたことも、たくさんありました。
自宅という環境で診療を行うことで患者さんの生活が外来に通院しているときよりも見えやすく、普段の様子を把握しやすいため、調子が悪い、いつもと様子が違うといったことに早めに気づくことができます。また、処方した薬をしっかりと患者さんが飲んでいるのか、インスリンは打てているのか、吸入はつかえているのか、サポートする家族はどんな人なのか、など治療を提供するうえで必要な情報がよくわかると思いました。
家族からもお話が聞けますし、本人からもライフレビューを通してその人の人生ドラマが映像として浮かび上がってきます。患者さんのことがよくわかりますし、同時に自分以外の人生もちょっぴり味わうことができてしまいます。
最終発表では、他国の在宅ケア、医療や介護のシステムを調べ、発表させていただきました。他国のシステムを知ることで、改めて日本の高齢化社会における今後の課題を考えるきっかけになりました。
他国のシステムを調べていく中で、また、この1か月のローテーションを通して、自宅で高齢者が過ごしていくということは、医療のサポートだけではなく介護のサポート、つまり医師以外の職種の方々の活躍あってこそだと改めて実感しました。
まだまだ医師としても家庭医としても未熟で、勉強することが山ほどあると実感しましたが、先生方が診療するうえでのちょっとしたもやもや・悩みを聞いてアドバイスをくださったので、さらに学びが深まっていきました。1か月間ありがとうございました。
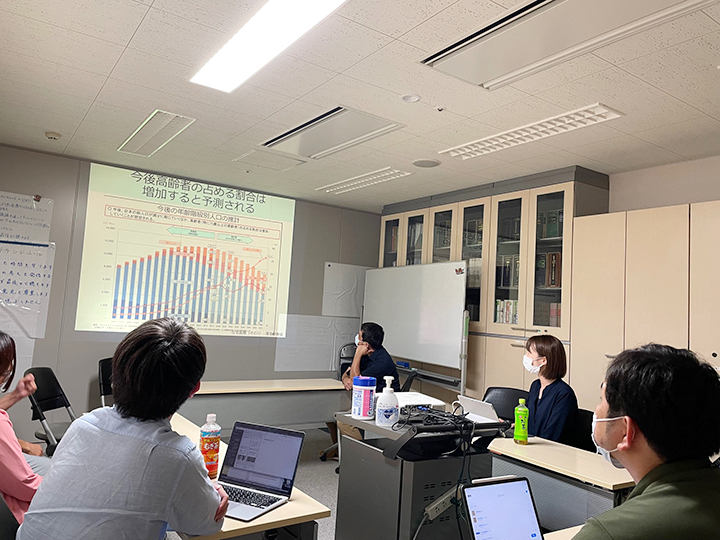
このサイトの監修者
 亀田総合病院
亀田総合病院
在宅診療科 部長 大川 薫
【専門分野】
家庭医療学 在宅医療

