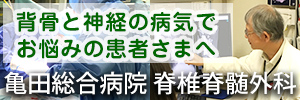飛魚を見たかー見ることとはー1
外科医の世界は封建的である。弟子は師匠・先輩の技術を見て盗む。言葉や文字では伝承できる技術は限られている。ところが、この「見る」ことは簡単ではない。自分に充分な予備知識がないと、先達の技術を見て盗むことはできない。
ウエブスターの辞書にはseeに11の意味を分類しているが、我が漢字民族も「みる」ことをとても大切にした民族と言えよう。「見る」「観る」「視る」「看る」「診る」と表現そのものも同音異句が多数存在する。「お見限り」「見切る」「人を見る」「看取る」「見破る」などなど。「味わう」「臭う」の持つ意味の多重性は「見る」の多重性にとうてい敵わない。ヒトの五感のうちで、視力情報の占める重大さがわかろうと言うものである。
視覚に関する研究は、解剖学を始め、神経生理学、心理学など非常に多彩な分野にまたがる。著者は大脳生理学は苦手なのであまり深く触れたくないが、大脳の情報処理能力に占める視覚情報の意味について、著者なりの考えを述べたい。
大脳生理学者マッケイによれば、視覚情報は網膜に入力された映像を脳が受け身で処理しているのでは無いと言う。脳の方に、ある準備状態が存在しないと、見えてはこない。脳の方の情報処理は単純な画像処理では無く、20もの専門分野が、明暗、色彩と言った単純なものから、動きの速度、方向、すでに記憶されている形象とのマッチングなどを瞬時に同時平行的に処理し、意識への投影を行っていると言う。
カエルでは特に動きに対する処理能力が最優先で、動かないものは認識されないと言う。目の前で動くものには一応食いついてみる。それが餌の蝿であろうと、悪餓鬼が、鮒釣りに飽きて、カエルの目の前で餌を動かして見たのかの区別はできない。餌であればそのまま飲み込み、餌でなければ吐き出してしまう。ところが、悪餓鬼の餌には針がついていて吐き出せず、あわれカエルは自由になったときには、尻からストローで入れられた空気で腹は膨らんでしまい、水に潜れない。カエルの視覚情報処理はかくも(動くもの=餌)という単純な構成で出来上がっている。
ヒトでは五感のうち特に視覚が最も発達しているが、カエルのように動きのあるもの、否、対象物の動きには抗し難い意識集中が起こってしまうものの、食いつこうと言う欲求までは引き起こさない。
※このコンテンツは、当科顧問橘滋國先生の著書である「体の反射のふしぎ学ー足がもつれないのはなぜ?」(講談社 ブルーバックス 1994年)を元に改変・編集したものです。
このサイトの監修者
 亀田総合病院
亀田総合病院
脊椎脊髄外科部長 久保田 基夫
【専門分野】
脊椎脊髄疾患、末梢神経疾患の外科治療