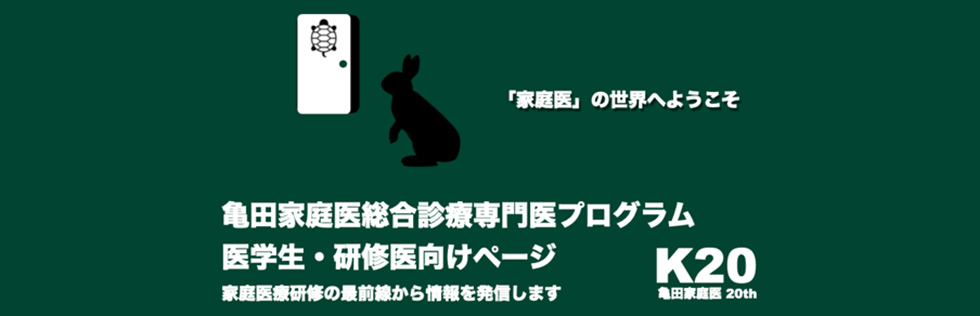スイッチの在処
エントリー
健康増進と疾病予防
キーワード
行動変容、思春期、小児肥満
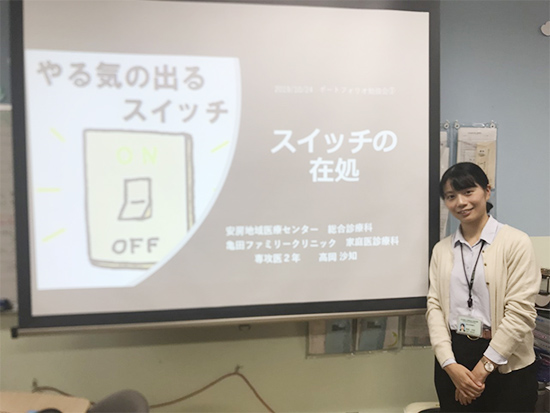
本日は、専攻医2年目の高岡先生によるポートフォリオ(の種)の発表でした。小児肥満の症例をとりあげ、思春期の小児の健康増進と疾病予防として行動変容をどのように実現すればよいか、討論しました。
皆さんは小児肥満の頻度をご存知でしょうか?12歳までの肥満の頻度は10%とされています(2014年文部科学省学校保健統計より)
"肥満"は状態であり、健康障害を合併したときに"肥満症"と定義されます。特に誘因がない原発性、器質的な疾患に続発する二次性に分けられ、小児の場合はBMIではなく、肥満度を指標として定義されます。(日本肥満学会ガイドラインより)
館山市では2001年から小児生活習慣病予防検診がなされており、小学校5年生、中学2年生で血液検査や腹囲測定で小児肥満やメタボリックシンドロームがスクリーニングされています。今回は学校の健診で指摘を受けて当院を受診された親子の症例でした。
相談に来た児童に器質的疾患はなく、日常の活動や生活習慣による原発性の肥満と考えられました。肥満の介入には日常生活や習慣の見直しが必要であり、行動変容が必要となります。初回の受診で目標設定が行われました。SMARTの法則を用いて主体的に、自己効力感を失わないように配慮して治療ゴールが共有されました。認知行動療法で肥満に陥りやすい7つの生活習慣からの脱却をはかり、ペアレントトレーニングを活用することで、行動変容は実行期となり、家族の協力もあり回数を追うごとに運動や食事の生活習慣の改善がなされていきました。野菜嫌いを克服、間食も減り、家族ぐるみでウォーキング、ゲームも減らして順調なようでした。しかし、半年後に運動、間食習慣は元に戻ってしまいました。思春期特有の反抗期で家族関係の変化があり、本人も家族も危機意識が薄れてしまったようです。
全体の討論では、本人の興味とマッチした行動を促せないか(ゲームでウォーキングなど)、実際に変わったときの体験談を話してみてはどうか、本人のモチベーションにつながるような心に響くカード(手段)を揃えてはどうか、時には少し無理な食事両方や減量をしてはどうか・・・など多数の意見があがりました。
岡田先生からは、学童期の肥満に対する長期的アウトカムの介入研究はなく、直接的な体重減少ではなく、食物の内容の見直し、健康な食べ方や運動習慣を増やすというプロセスに注目し、健康によってやりたいことができることが健康増進につながるのではないか、というコメントをいただきました。
行動変容は時間がかかり、継続することが難しいプロセスです。本人にとって健康であることの意味、健康であることで何をしたいか、本人の望む生活のスタイルは何か、患者様と話しあっていくことが行動変容のキーになると感じました。
文責:塚原麻希子
このサイトの監修者
 亀田ファミリークリニック館山
亀田ファミリークリニック館山
院長 岡田 唯男
【専門分野】
家庭医療学、公衆衛生学、指導医養成、マタニティケア、慢性疾患、健康増進、プライマリケア・スポーツ医学