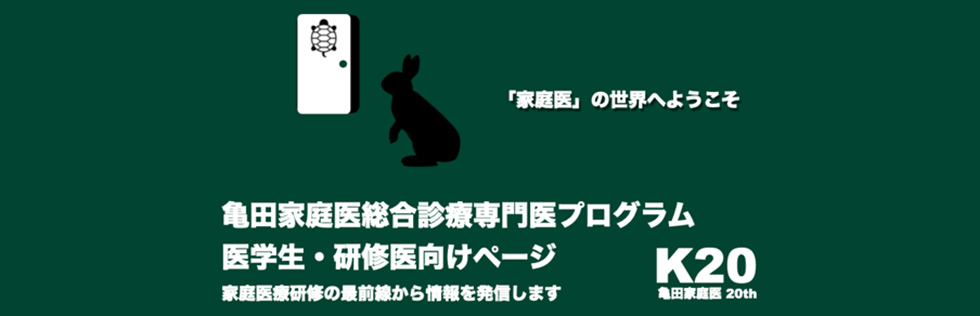李先生 7月ローテの振り返り
亀田総合病院産婦人科コースの初期2年次の李先生が、7月の1ヶ月KFCT
をローテしてくれました。研修発表をシェアします。
-----------------
これまでの臨床研修で気になっていた「疾患以外」に苦しむ患者さんたち。
入院をできる限り必要としない人生のためには何ができるのか?
「処方屋さん」にならない外来はどうすればできるのか?
葛藤状態にある人が、立ち直るためには何ができるのか?
そんな思いを胸にやってきたKFCTローテでは以下の疑問を抱いていた。
- 家庭医と総合内科医の外来は何が違うのか?
- 家庭医を目指す先生ってなんでそんなに家庭医に惹かれるの?
- 家庭医の頭の中ってどうなっているの?
- 家庭医は、患者さんをちょっとhappyにして帰しているのではないか?
ローテを通じて気付いたのは、「家庭医はそこに病気があるかないかはあまり関係ない」ということ。
これまで感じていた「自分の外来でできることは本当に少ないのではないか。自分がいくら努力してもその人たちを助けられる保証はない」という思い。
問題の「下流」では、効果も実感しやすいので患者も医療者も頑張れるが、「上流」では本当に意味があるのか実感できない。
その問題意識への答えとして、以下の気づきを得た。
- バケツの水の1滴:混沌から抜け出す1滴がいつかくるよう、そこにつながっていると願って、自分の1滴も注ぐ。
- 健康因Salutogen:病因Pathogenの総和を上回る健康因Salutogenをつくれれば、その人を支えられるのではないか。
また、成人だけでなく、小児や整形、メンタルヘルスなど多くの患者さんと会う中で、「"みよう"と思っていなければ"診れない"し、"見れない"」
「うちの専門ではない」という思考が、医師本人の能力とは関係なく、診る姿勢から遠ざけているのではないか。自分の勝手な意識で患者をみることをやめていたのではないかと気づいたそうです。
13歳で知った途上国で暮らす同世代の少女の生活
https://www.plan-international.jp/girl/special/index_s.html
そこから「発展途上国の女性のreproductive health and rights」がlife missionとなった。家庭医療を学ぶ中で、コンテキストという視点で、自分では制御できないものに左右されて生活する人々として考えられるようになった。
今後の診療やlife missionの中で
- どのような環境に生きる人でも自分の健康を気遣う方法を伝える
- 自分や周りがhappyに生きることの意味を考えてもらう機会を持ってもらう
- ヘルスリテラシーを高める
これらを通じて、自分自身がその人の小さな健康因になれるように。
-----------------
日々の臨床の中でのモヤモヤに対する答えが、家庭医療の中にあるのではないかという姿勢で、ローテに来られた李先生。こちらも驚くほど貪欲に家庭医療学を学ばれて、最終発表でまとめられていました。
モヤモヤをそのままにせず言語化しようとする姿勢に、こちらも刺激をいただきた1ヶ月でした。またぜひKFCTへ!

このサイトの監修者
 亀田ファミリークリニック館山
亀田ファミリークリニック館山
院長 岡田 唯男
【専門分野】
家庭医療学、公衆衛生学、指導医養成、マタニティケア、慢性疾患、健康増進、プライマリケア・スポーツ医学