シン・アイオワ便り1 「USMLE受験することなくファカルティ!?」
アイオワ大学麻酔科
Clinical Associate Professor
杉山大介
2025年1月よりアイオワ大学麻酔科にて勤務している杉山です。こちらに来て半年が経過しようとしています。それまでは亀田総合病院麻酔科にて部長を務めさせていただいており、今回現・亀田総合病院麻酔科主任部長の植田先生よりアイオワ便りを継続的に連載してもらいたいとの依頼をいただき、僭越ながら引き受けさせていただきます。アイオワはアメリカの中西部に位置するとても田舎の場所です。一般的に華やかな感じで世の中に出回っている東海岸のアイビーリーグの大学への留学情報や西海岸のカリフォルニア大学などの情報とはまた大きく異なるアメリカの地方での臨床の情報や、将来的に海外での臨床や研究留学を志す先生方に何か少しでもお役に立てるような情報をお届けできたらいいなと思います。
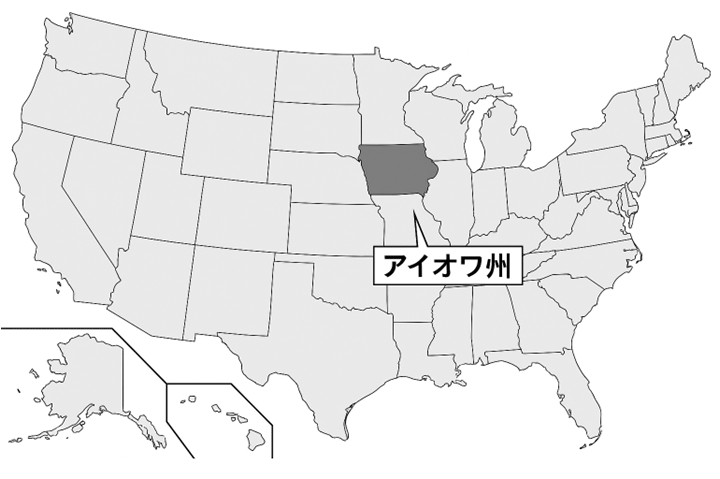
私は元々は信州大学麻酔科で麻酔科医としてのキャリアをスタートし、その後信州大学大学院で博士号を取得させていただきました。2014年からの5年間は、アイオワ大学麻酔科の基礎研究室でポスドクとして研究に従事しました。そこで、臨床で活躍されていた植田先生、さらに当時半年間留学中だった亀田俊明先生(現・亀田総合病院院長)と出会い、多くの刺激と学びを得ました。このご縁をきっかけに、2019年の帰国後には亀田総合病院麻酔科で勤務することになり、非常に多様な症例や、国際的な視野を持つチームでの経験を重ねました。そして今、再びアイオワの地に戻り、今度は臨床医として新たな挑戦を続けています。
シン・アイオワ便りと銘打ちましたが、私が今回レジデンシーなどを経ずに直接ファカルティとして勤務しているのは、通常米国で医師として働く”王道”とは著しく異なるものです。ご存じの方も多いとは思いますが、日本の医学部を卒業してからアメリカでも医師として勤務する一般的な方法は「USライセンス取得」と「レジデンシー修了」になります。つまり、通常は米国医師国家試験であるUSMLE試験(現在はSTEP1、STEP2CK、STEP3の3つの試験で構成)に合格してECFMG(Educational Commission for Foreign Medical Graduates)認証を取得する必要があります。そしてその上でアメリカのレジデンシープログラムにマッチングし、アメリカ国内でレジデンシー(専門研修)を受けて修了しABA(American Board of Anesthesiology: アメリカの麻酔科専門医)を取得しなくてはなりません。このレジデンシーは麻酔科であれば4年を要するものです。しかし、私の場合は、植田先生のご推薦をいただき、これまでの研究・臨床実績、日本の医師資格・麻酔科専門医資格、そしてTOEFLのスコアなどをもとに、アイオワ州よりスペシャルライセンスを発行してもらう形で、大学から雇用されました。非常にありがたいことで、ここまでのご縁とこれまでの環境に感謝しています。こうした道もあるということを、今後臨床留学を考える方に知っていただければ幸いです。
これが自分にとってどのぐらい夢のような話かを説明するために、自分のこれまでの経緯を書きたいと思います。基礎研究留学していた頃、私は毎日動物センター直下の動物臭が漂う研究室で毎日真っ暗な部屋でラットやマウスと朝から晩まで過ごす生活をしていました。日本では難しかった臨床に忙殺されることなく実験や研究に没頭できる自由を手にして幸せを感じる一方で、臨床や臨床研究に取り組んでいた植田先生の姿は非常に華やかで、自分自身の麻酔科医としての矜持や挑戦心を強く刺激されたのを覚えています。そんな中で当時研究室のボスだったDr. BrennanからAlternate pathwayに推薦するので挑戦してみないかというお誘いをいただきました。Alternate pathwayというのは、簡単に言うと他国で麻酔科専門医を取得済みの人がアメリカ国内で5年間指導者として勤務することで、レジデンシーを経ることなくアメリカでの専門医試験を受験することのできるコースです。当時のアイオワ大学麻酔科主任教授だったDr. Toddにも了承いただいてUSMLEに合格したら臨床勤務させていただける話になっていたところで、大学内での政治的な動きの中で主任教授のDr. Todd (研究大好きで基礎研究含めて研究をする人をすごく重視してくれていた)が急にアイオワ大学から去られました。後任であり現在もアイオワ大学麻酔科の主任教授であるDr. WongにDr. Brennanから再度話していただいて、Alternate pathwayの話は継続できそうだったところで、今度はDr. Brennanが健康上の理由から退職されることになり、ラボも閉鎖されることになりました。私は後ろ盾を完全に失い、どうしようかと迷っている折、亀田俊明院長からもし帰国するのであれば是非亀田にとお誘いをいただきました。それまで信州大学麻酔科で成長させていただいた恩もありどう身を処すべきか大変迷いましたが、一旦アメリカでの挑戦は諦めて(その意味では大きな挫折でした)新天地である亀田での勤務を開始しました。その後の6年間は、植田先生と共に手術室運営を担い、日本でも有数のハイボリュームセンターでの実務や、若手医師と切磋琢磨する機会に恵まれ、臨床研究についても多くのことを学ばせていただきました。とても充実した日々ではありましたが、年齢を重ねる中で「このまま安定した毎日に着地してしまうのでは」という漠然とした不安も常に心にありました。歳をとったとはいえまだ麻酔科医としての人生はちょうど半分を過ぎたぐらいのところで、ここから先何かまた大きな挑戦をすることができるのか、挑戦できるとしたらなんなのか、などたくさんのことを考えました。そんなときにいただいた今回のアイオワ大学からのオファーは、かつて諦めた夢が再び形を変えて戻ってきたかのように感じられ、迷わず「ぜひ行かせてください」と即答しました。
通常の経路を経て渡米し臨床をしている多くの先生方からすれば、まるで裏口入学のように感じられるのではないかとも思います。ただ、これはアイオワのようなアメリカの田舎の大学が抱える日本と同様の問題に起因して生じており、私たち米国外の医師に訪れているチャンスでもあるようです。日本と同じで、アメリカでも手術件数の増大が経営に直結するため、アイオワ大学でも手術件数の増加は重要な命題で、毎年手術件数は右肩上がりです。しかし、これは全米でどの病院でも同様の状況なため、麻酔科医は取り合いの状況で西海岸や東海岸の都市部や、より金銭的に条件の良いところに偏在してしまうようです。そうなるとアイオワのような立地的に厳しい場所では、どうしても麻酔科医のリクルートが難しいです。一方でアイオワ大学にアイオワ州の医療は集約化されているため、アイオワの医療を支えるためにも麻酔科医は必要で、その結果私が採用されたようなスペシャルライセンスを発行してのInternational Facultyの雇用に至っているようです。そして求められているのは技術知識が確立していて教育を行えるある意味即戦力の人材ですので、私のような中年以降の人間がアメリカでのトレーニングも受けたことがないのにいきなり採用してもらえるような状況が起きているのです。
亀田総合病院とアイオワ大学麻酔科のつながりは強く、元々アイオワ大学麻酔科で心臓血管麻酔部門のDivision Chiefをなさっていた植田先生は、現在もアイオワ大学麻酔科Emeritus Associate Professorの立場にあり、日本で誰かアイオワに来たがっている麻酔科医はいないか、推薦してもらえるような麻酔科医はいないかと今も定期的にこちらの主任教授のDr. Wongとやりとりをしているようです。現時点でも私に続いて亀田麻酔科出身の先生がアイオワ大学麻酔科に赴任する予定もあります。また、亀田麻酔科専攻医プログラム出身の先生が、渡米を目指している中で、レジデンシーやフェロー先の候補としてアイオワ大学も含める動きもありました。ありがたいことに、現在私はClinical Associate Professorのポジション(アイオワ大学で採用される場合のtrackの話はまた次回以降にしたいと考えています)をいただいており、アイオワ大学に応募した人がいる時に、その人がどのような人なのか、採用をどうしたらよいかなどの意見を聞かれることも多いです。現在すでに亀田とアイオワの共同研究を始めておりますが、今後そちらもますます拡大していけたらと考えています。亀田総合病院麻酔科とアイオワ大学麻酔科の結びつきは今後ますます強くなるような気がしています。
このサイトの監修者
 亀田総合病院 副院長 / 麻酔科 主任部長/亀田総合研究所長/臨床研究推進室長/周術期管理センター長 植田 健一
亀田総合病院 副院長 / 麻酔科 主任部長/亀田総合研究所長/臨床研究推進室長/周術期管理センター長 植田 健一
【専門分野】小児・成人心臓麻酔

