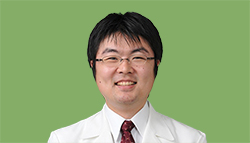今回のテーマは便秘です。子供の便秘はそれほど珍しくありません。子供の便が出にくいということで悩まれたお父さんお母さんも少なくないことでしょう。
小児の便秘はほとんどの場合、小児科(小児内科)で診られることが多いです。しかし中には頑固な便秘の子がいます。頑固な便秘の子供の中に、Hirschsprung(ヒルシュスプルング)病という腸の神経が育っていないために便を上手く出せない病気(の中の軽症な方)が紛れていると言われるため、小児外科へ相談されることがあります。
生まれたばかりの赤ちゃんは1日に3~6回の排便をするのが一般的です。人工乳の子は回数が少なく、母乳の子は回数が多い傾向があります。月齢をかさね、生後半年から1歳くらいになると排便回数が1日に1~2回くらいに落ち着いてきます。離乳食を始めると便がかたまってきます。
排便習慣は人それぞれで多少の偏りはありますが、硬い日もあれば柔らかい日もあります。大人なら便が硬いとき、痛くてもこれを出さないと良くならないのをわかっているので、頑張って息んで出すことでしょう。しかし子供はそうしません。痛いと思ったら排便を我慢しちゃいます。我慢しちゃえば便は貯まっていき、さらに便が硬くなります。便が硬いからさらに排便を我慢するという悪循環に陥ってしまうことがあります。ひどい場合、肛門近くに大量の硬い便が詰まってしまって出すことができなくなり、その脇を下痢便が本人の意図無く漏れ出る便失禁の状態(overflow incontinence)となってしまうことがあります。
便秘に対する薬、治療法は大きくわけて3種類あります。
-
緩下剤:便を柔らかくします。飲んだ薬が便になって出る頃に効くので即効性はありません。緩下剤の中で3種類の薬に分けられます。
- 塩類下剤:最も多く使われる薬です。薬が水分を引っ張ってきて便を柔らかくします。酸化マグネシウム、カマ、マグミットなどがあります。小児ではミルマグという液状の物もあります。比較的飲みやすい薬ですが、効き過ぎると下痢になるという欠点があります。
- 膨脹性下剤:薬自体が水を吸って膨らみ、ムース状の便にしてくれます。効き過ぎても下痢になることはありません。バルコーゼというのがあります。便秘に対して非常に有効な薬なのですが、飲みにくいのが欠点です。粉状の薬で水に溶けません。水で飲むと口の中にパサついて残ってしまい、大人でも慣れが必要です。飲みにくいです。味はほんのり甘く苦みは無いので、ヨーグルトなどに混ぜると(舌触りは悪いですが)飲める子が多いです。
- 糖類下剤:ラクツロースなど。大人の肝硬変の患者さんによく使われます。甘くて飲みやすい液状の薬ですが、効果は弱めです。
- 大腸刺激剤:腸を動かして便を出すようにします。夜寝る前に飲んで、翌朝に効いてきます。小児ではラキソベロン、ピコスルファートという液状の物が使われます。大人でよく飲まれるプルゼニド、CMでおなじみのコーラックなども同様の効果です。効き過ぎると蠕動痛(ぜんどうつう)でおなかが痛くなることがあります。長期間使用すると効きにくくなり徐々に使用量が増えるという欠点があります。
- 肛門からの直接刺激:浣腸や綿棒、“こより”などで刺激を加えます。便がすぐ近くに降りてきていれば効果があります。浣腸や綿棒で腸を傷つける事がありますので、注意してください。
個性の出てくる2~3歳に偏食が進んだり、水分を飲まなくなったり、便秘の原因はさまざまです。それぞれの治療法にも利点・欠点がありますので、外来で相談しながら治療法を選択することをおすすめいたします。
小児外科 松田 諭