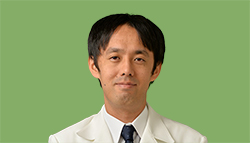皆様、こんにちは。腎臓高血圧内科の井上友彦と申します。今回はあまり馴染みのない検査である腎生検についてお話しさせていただきます。
腎生検の目的
病院や健康診断での検査で「尿に血液が混じっている」、「尿からタンパク質が出てしまっている」、「クレアチニンという腎臓の機能を示す数値がいつもより高く(悪く)なっている」と言われることがあります。
このような時、腎臓にダメージを与えている原因が存在するのですが、採血や尿検査、CT検査、超音波検査などの一般的な検査だけでは、原因を特定できないことがあります。
そのため、原因と腎臓の状態を把握し、どのような治療を行うのが適切かを判断する目的で行われるのが腎生検です。
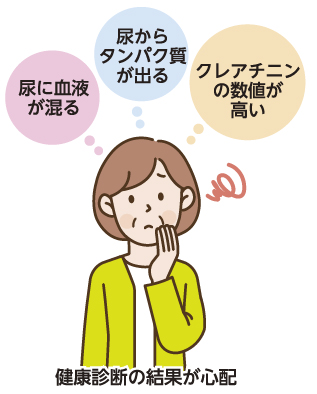
検査方法
腎生検は、実際に対象となる患者さまの腎臓の組織を後述する方法で採取し、その組織を顕微鏡で観察することで、何が起きているのかを直接確認します。
主には、皆様も理科の授業で触ったことがある顕微鏡を用いて観察する光学顕微鏡観察、特定のタンパク質に反応する抗体を振り撒ま いて、その抗体が腎組織のどこに付着しているかを評価する蛍光免疫染色法での観察、電子線を当てることで光学顕微鏡観察よりも微細な領域まで観察する電子顕微鏡観察があります。
これらの所見を総合して、原因(病名)や検査時点での腎臓の状態(ダメージを受け続けているのか、自然に回復する可能性があるのか、治療の効果が見込めるのか)を診断し、治療方針を決定します。

実際の流れ
当院では、基本的に3泊4日の入院で超音波ガイド下での針生検を行います。検査前日に入院していただき、全身状態を確認して腎生検が行えるかどうか、最終確認を行います。
検査の流れ
- 検査当日は後に示すとおり、検査後は翌朝までベッド上で仰向けのまま安静にしていただく必要があるため、トイレのかわりに尿道バルーンカテーテルという自然に尿を排泄させるための管を挿入します。また、検査後にお薬(再出血を予防するための止血促進剤)を投与するため、点滴も確保します。
- これらが完了したら、ベッドでうつ伏せになり、超音波検査で腎臓の組織を採取する針を刺す場所を決め、消毒し、局所麻酔を行います。
- その後、超音波を確認しながら針を進め、腎臓の組織を2〜3 回ほど採取します。採取が完了したら、針を刺した場所を圧迫止血し、仰向けに戻り、検査自体は終了となります。この後は、腎臓からの再出血を避けるため、検査の翌朝まで仰向けのままベッド上安静となります。
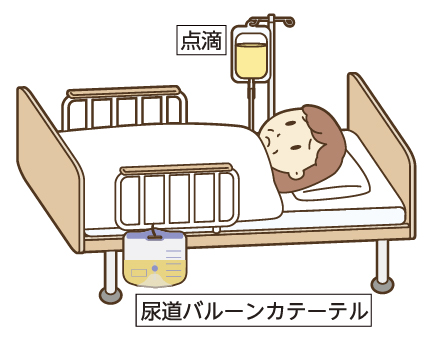
入院が必要な検査にはなりますが、検査を行うことで腎機能を改善させるための糸口をみつけ、腎機能の悪化防止のために適切な治療を選択できます。透析の導入を避けることにもつながる非常に重要な検査です。もし、腎生検が必要となった場合は、大事な腎臓を守るためにも一緒に頑張りましょう。