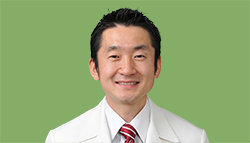1. 膀胱のはたらき
尿失禁について理解するまえに、ふだん尿をしているあなた自身を考えてみましょう。腎臓で作られた尿は膀胱にためられ、ある時間に尿がしたくなりトイレに行き、便器に座り尿をしています。しかし、尿をためようと思っていてたまったのでもなく、便器に座り尿をしようと意識したわけでもないのに、ときに、自然に尿が出ていることに、気づかされます。このように膀胱は、あなたが意識することなく、尿をためて(蓄尿といいます)、尿をする(排尿といいます)相反する二つの機能をはたしています。
膀胱は排尿時に膀胱を収縮させる働きをもつ排尿筋でとりかこまれ、尿道の入口には内尿道括約筋があります。尿がたまっていく蓄尿期には排尿筋は弛緩していますが、内尿道括約筋はしっかり収縮しています。しかし排尿の時には、排尿筋が収縮してない尿道括約筋は弛緩します。自律神経のはたらきでスムーズに機能しています。したがって膀胱の自律神経に影響をあたえる神経の病気や骨盤の手術後、薬物の服用の場合には排尿の働きに障害が生じることがあります。
2. 尿がでにくい(排尿困難)
骨盤臓器脱のなかでも、膀胱瘤がある程度進行した状態になると、尿がでにくい、尿の勢いがない、排尿をおえても残った感じがある等の症状がみられます。これは、1.尿道の膀胱に近い部分が膀胱の下垂につられて下方にひきおろされますので、尿道の屈曲が強くなり尿が出にくいことと、2.膀胱のかなりの部分が膣の外に脱出した状態では膀胱の収縮機能が低下しており、膀胱の排尿筋が十分に収縮できないために尿を排出しがたいこと、3.排尿に合わせて腹圧の動作をおこなっても、膀胱が膣の外にあれば腹圧は、膀胱内の尿を排出するのには作用せず、むしろ脱出した膀胱がいっそう外にむかって脱出する方向に作用することになり、尿は出にくいままなのです。
3. 尿が近い(頻尿)
排尿の回数が多く、日常生活に不便をきたしている状態で、通常は朝起床してから夜床につくまでの排尿の回数は7回までは正常範囲とされ8回以上を昼間頻尿とします、就寝後の夜間排尿回数は1回以上あれば夜間頻尿とされます。
頻尿で診療施設を受診されるときには、1日の排尿の時間、回数、尿量などを記録した排尿日誌を(3日間ぐらい)つけてから受診されると診断の助けになります。
4. 尿もれ(尿失禁)
女性での尿失禁は頻度の高いもので健康女性の約20%にみられます(中には40%との報告もあります)。尿失禁の9割は、せき、くしゃみ、走る、階段をおりるなどの動作時に尿がもれる腹圧性尿失禁と、トイレが間に合わずにもれる、強い尿意が我慢できずにもれる切迫性尿失禁、その両方の要素がある混合性尿失禁に大きく分類されます。そのほかには身体機能障害でトイレにたどり着けずにもれたり、排尿にかかわる神経の障害で排尿困難となり膀胱内に尿があふれてもれるなどの場合があります。
尿失禁で診療施設を受診されるときには、3日間の排尿の時間、回数、尿量、そしてお茶、水など水分を取った量すべてを記録した排尿日誌をつけてから受診されると診断の助けになります。
女性の尿失禁の分類
- 切迫性尿失禁
- 腹圧性尿失禁
- 混合性尿失禁
その他の尿失禁
- 機能性尿失禁
- 溢流性尿失禁
尿失禁の頻度
日本の看護師21歳代から65歳までの3,730人でのアンケート調査の結果によると全体の平均19.4%に尿失禁がありました。年齢では40歳代後半では約40%の看護師が尿もれありと回答していました。
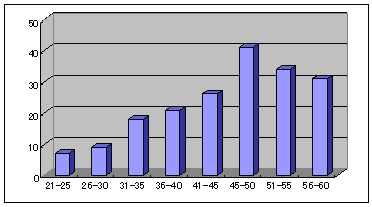
女性の尿失禁の割合
これまでにいくつかの尿失禁についてのアンケート調査が行われていますが、滋賀県在住の女性968人で調査したデータでは腹圧性尿失禁が63%、切迫性尿失禁が13%、混合性尿失禁が24%であったとの報告があります。
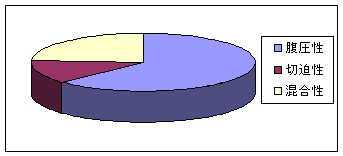
5. 切迫性尿失禁
トイレが間に合わずに尿がもれる、急に強い尿意が出てもれてしまうタイプの尿もれを切迫性尿失禁といいます。この原因は膀胱の過活動性により膀胱の排尿筋が収縮しやすくなってもれるもので、ほかにも神経の病気、膀胱炎、膀胱結石などでも同様の症状があります。
6. 腹圧性尿失禁

咳やくしゃみのとき、走ったり、階段を下りるとき、また重いものを持ち上げるときなど腹圧がかかる動作をしたときに、不意に尿が漏れる状態を腹圧性尿失禁といいます。これは尿道の入口にある尿道を閉める働きのある内尿道括約筋の緊張低下の場合(内尿道括約筋機能不全)と、尿道を支える組織が弛緩したために、急に腹圧が上昇し膀胱内の圧もたかまったとき尿道をしめつけるはたらきがうまく作動せず尿漏れがおこる場合(尿道過可動性)があります。
7. 尿失禁の薬物療法
切迫性尿失禁に対し抗コリン薬がまず使用されます。これは切迫性尿失禁の原因である過活動膀胱に対し膀胱排尿筋の収縮をおさえると同時に膀胱の過敏性も抑えると考えられ、頻尿、尿失禁をかなり改善します。副作用としては口が渇く症状や便秘が出ることがあります。また緑内障治療中の方は、抗コリン剤の服用には注意が必要です。かかりつけの眼科医に使用の許可を得てから服用しましょう。
8. 尿失禁の手術療法(TVT手術、TOT手術)
腹圧性尿失禁に対しては手術療法が第一に選択されます。1世紀以上にわたり100種類以上の手術法が報告されてきましたが、現在世界的にもっとも実施されているのがTVTスリング手術です。TVTはtension-free vaginal tapeの略で前膣壁の尿道の中間部分に相当する前膣壁を小切開してここから恥骨の裏側を経由して下腹部にポリプロピレンのテープを通し、咳などで腹圧がかかったときに尿道をしっかりと支持することで尿道の機能的な閉鎖→尿漏れを防ぐという手術法です。TVT手術では術中に膀胱へ傷がついていないかを内視鏡(膀胱鏡)で確認する作業が必要であること、テープ引き上げの調節が微妙であることから、最近TOT手術が試みられています、TOT手術では、骨盤臓器脱のメッシュ手術と同様に、閉鎖孔に尿道をささえるテープを通しますので内視鏡操作が不要で術後の排尿困難のリスクもすくない利点があります。
TVT、TOTのいずれも治療効果にすぐれた方法です。当科では、TVT、TOTを実施しています。
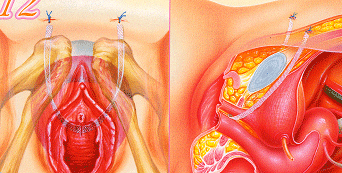
9. 過活動膀胱(OAB : overactive bladder )
尿意切迫感(急におこる強い尿意で、トイレを我慢しがたい感じ)を主な症状とし、頻尿(通常は夜間頻尿)、場合によっては切迫性尿失禁を伴う症状症候群。診断には特殊な検査は必要なく、おもに自覚症状に基づいて(OABSSなどの質問表を用いて)診断されます。
日本人の約8人に1人、約800万人にのぼると推定され、高齢化社会にはいり患者数は増加すると予想されています。過活動膀胱の治療には抗コリン剤による薬物療法が中心となります。一般に抗コリン剤は症状の改善に有効です。
副作用に口内乾燥があります。
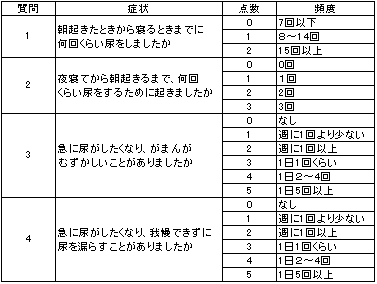
過活動膀胱の診断には、左記の質問項目の3で、2点以上、かつ、全体で3点以上が対象となります。
症状の重症度評価では、合計スコアが5点以下を軽症、6~11点を中等症、12点以上が重症とされます。
10. 便失禁(出産時の肛門括約筋損傷によるもの)
分娩時に会陰切開や自然経過で裂傷が生じて肛門括約筋が損傷し、創の修復治癒が不完全な状態の場合に、分娩後比較的早い時期から肛門括約筋の収縮機能不全の症状として、おならを我慢できない(ガス失禁といいます)、水様の下痢便がもれる、下痢便の際にトイレが間に合わない、下着が便で汚れるなどの症状がみられることがあります。このような症状を肛門括約筋不全といい、ガスが漏れること、便が漏れることを合わせて便失禁と表現します。この便失禁はQOLを著しく損ねるもので、患者さんにはとてもつらいものですが、羞恥心から実際には受診されることが少ないのです。欧米では便失禁はウロギネ分野で重要な疾患と考えられています。
分娩時の産道損傷に原因する肛門括約筋機能不全の治療としては手術が有効です。手術は肛門と膣との間を切開して肛門を締める働きをもつ肛門括約筋を探し、離れた肛門括約筋の断端同士を縫合します。脊椎麻酔で手術をおこないます。約1週間の入院が必要です。当科ではこの便失禁の手術を実施しています。