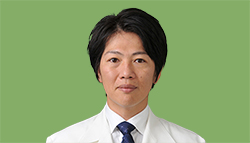多くの因子が不妊の原因になることが知られています。今回は不妊にも関わり、女性を悩ますことの多い子宮内膜症と多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)のお話です。
子宮内膜症
子宮内膜症は、子宮の内側を覆う膜(子宮内膜)と同じような組織が子宮の外に広がった病気で、病気が悪くなるとひどい生理痛や、慢性の下腹部痛、性交時の 痛みや不正性器出血、生理の時期の排尿痛や生理前の便秘、生理後の下痢などの症状が現れます。20歳から40歳代の女性の10%、不妊で悩む女性の約 30%に起こることから、珍しい病気ではありませんが、痛みが生理や性交と関わるために他人に相談できずに悩んでいる女性も多いようです。
病気の 起こる原因はまだはっきりと解っていませんが、女性ホルモン(主にエストロゲン)で増殖し、生理の時には剥がれて出血するという子宮内膜と同じような性質 を持ちます。生理の周期に合わせて増殖と剥離・出血を繰り返すために、初期は点状の病変ですが、子宮の周囲の卵巣、卵管、腸、膀胱に慢性の炎症が生じ、進 行すると、卵巣や卵管の腫大、相互の癒着(くっつくこと)が生じ、上で述べたような症状が起きます。
産婦人科を受診し、症状を話し、診察を受け、超音波検査や MRI などの画像検査を受けると診断が可能ですが、しっかり診断するためにはお腹の中を内視鏡で観察する腹腔鏡検査が必要になります。 治療には、
- 生理時の痛みをコントロールするために鎮痛剤や漢方薬を使用する治療法
- ピルを用いる治療法
- 女性ホルモンを下げて病変を萎縮させる治療法(GnRH アナログ)
- 女性ホルモンと拮抗する男性ホルモン様の薬を用いる治療法(ダナゾール)
- 手術をして病変を除去する治療法
などがあります。
しかし、病変が完全になくなることは難しく、治療後もしばらくすると、病変が現れ症状が再び起こることが多いため、病気とうまく付き合っていく必要があります。一般的には、女性ホルモンが減少し、生理がなくなる時期には症状から解放され、治癒します。
妊 娠に関わる部分に変化が起こることから、妊娠がしづらくなり不妊症となる女性もいます。ピル、アナログ、ダナゾールの治療の間は妊娠できないこと、妊娠の ために女性ホルモンを上げると病変が悪化しやすいこと、またいったん薬や手術治療しても再発しやすいことから治療がむずかしい面があります。信頼できる医 師に相談をし、病気を理解することが大切です。
多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)
月経が来ない(無月経)、あるいは月経が不順なために、産婦人科を訪れる患者さまに比較的多く見られる病気で、排卵障害による不妊の主要な原因の一つです。
月経の異常(無月経、月経不順)の他に、下で述べるような特徴的なホルモンバランス、超音波検査での卵巣の像で診断されますが、生殖年齢の約5%がこの状態であると言われます。
- 超音波で卵巣に卵子を含むはれもの(卵胞)の未熟な小さいものが多数観察される
- 脳から分泌されて卵巣に働く2つのホルモン、FSH(主に卵の成長に働く)と LH(主に排卵の刺激となる)のバランスが通常と異なり、LH が過剰となっている
- 男性ホルモンが高いために多毛やにきびがある
- 糖尿病などの糖代謝異常があり肥満体型であるなどの特徴があります。欧米と日本では症状の現れ方が異なることが知られ、日本では月経異常と1と2で主に診断されます。
漢方薬で体質を改善する方法もありますが、通常はクエン酸クロミフェン(クロミッドRなど)という経口の排卵誘発剤が使用され、約70%の女性で月経が回復します。無効な場合には、注射の排卵誘発剤、糖尿病の治療薬、副腎ステロイド併用が必要になります。
比較的治療しやすい病気ですが、治療が難しいものもあり、また、排卵誘発剤では複数の卵が排卵される可能性があるため多胎妊娠のリスクもあります。