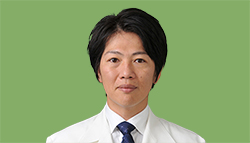加齢による卵の質の低下が妊娠の障害に・・・
成熟した卵子を排出し、女性ホルモンを産生する場所であることから、卵巣は女性らしさを作り出す中心的な臓器です。卵巣の機能が停止すると、女性ホルモン の産生が終わり、生理が来なくなって閉経を迎えます。ホルモンの低下に伴ういわゆる更年期の症状が出現するのは45歳位からですが、卵の質から考えるとそ の以前から卵巣の機能低下が始まっていることが明らかになってきました。
体外受精は、卵巣から排卵前に卵を採取して、体の外で精子と出会わせ、発 育した受精卵を子宮に戻して妊娠を目指す最先端の不妊治療の一つですが、自分の卵を用いる場合は、妊娠の効率は34歳までは変わりませんが、35歳以降に 急激に低下して、40歳を超えると確率的にはかなり難しくなるようです。2002年の米国の統計では、体外受精1回あたりで出産まで至る妊娠の効率は、 34歳以下で35~40%、39歳で20%,42歳で9%、44歳以上では2%と報告されています。米国では、他人の卵を用いた体外受精が認められてお り、その場合には卵を戻す女性の年齢による妊娠率の低下が見られないことから、加齢による卵の質の低下が妊娠の障害となるようです。
一方、男性は 加齢による男性ホルモンのゆるやかな低下を40歳以降に認めるものの、個人差は有りますが、老年期に至っても生殖の能力は維持されます。この男女の生殖能 力の差は、女性は体内で胎児を育てることから、他の臓器の加齢が進み機能低下が起きる以前に、からだに負担のかかる妊娠、出産、子育てを終了するという意 味で生物学上は利点があったと思われますが、文明が進歩し、医学が進み、価値観が多様化した現代社会では、女性の不利益となっているもの事実です。
女性の年齢による生殖能力の低下を科学の力でもとに戻すことは可能なのでしょうか?
残念ながら、卵子と精子の造りだされ方に差があるためになかなか難しいかもしれません。男性では精子の元となる細胞(精原細胞)は、思春期以降も増殖が可 能で、その細胞から新たな精子がつくり出されます(約74日)。一方、女性では卵子の元となる細胞(卵原細胞)の増殖は、その女性が母親の体内にいる間に 増殖を終了して(最大時700万個)、出生以前に卵子への変化(分化)が始まり途中で休止した状態で思春期を迎えます。その後、そのごく一部(一生の間に 約400~500個)が成熟して排卵されます。排卵される卵は選りすぐりの超エリートですが、排卵されるまでの間(35歳なら35年間、40歳なら40年 間)、自然の放射能や環境汚染物質などの影響を受けるため、質が低下し、それが妊娠のし易さの低下として統計的に明らかになるのが35歳以降であると言え ます。
そこで、不妊症専門医から、妊娠を考えている女性への助言は、
- 女性の生殖能力には年齢による限界があることを知って人生設計をたてること、
- 35歳を過ぎて妊娠を望む場合は、不妊症の専門医に相談をすることが望ましいこと、
- 卵巣の機能の低下を引き起こすタバコと過剰なアルコール、カフェインの摂取、過剰なダイエットは控えること
です。