虫歯や歯周病、または交通事故などが原因で歯を喪失してしまったら...
人間は食べることで生命を維持し、文化的な生活を営んでいます。したがって、無くなった歯をもとどおり取り戻したいと考えるのは、ごく自然な欲求でしょう。現在、取り外し型の義歯やブリッジ治療に代わる選択肢として、多くの人に知られるようになったインプラント療法。それは、人工的な歯の根(人工歯根)を顎に埋めて、その上に歯の形(上部構造)を作り、歯本来の機能を回復させる治療法です。
インプラント療法の歴史は20世紀初頭に遡ります。『IMPLANT=埋め込む』という言葉通り、ステンレスやコバルトクロム合金、金、サファイヤなどを利用した方法が試されてきました。しかし、人体は異物を感知すると体外に排出する性質を持っているため、数年後にはインプラントと顎骨の間に炎症が発生し、抜け落ちていたのです。1952年スウェーデン、イエテボリ大学のブローネマルク博士はウサギの骨に生態顕微鏡を取り付け、血流を調べる実験を行っていました。数ヶ月にわたる実験を終え、装置を骨から外そうとすると骨とチタンが結合し、取れなくなっていました。ブローネマルク教授は当時を振り返り、高い実験装置が駄目になったと悔やんだというエピソードが残っていますが、その時にチタンと骨を接触させ、数ヶ月安静にしておくと非常に強く結合することが発見され、この現象はブローネマルク氏によって、オッセオインテグレーション(オッセオ=骨の、インテグレーション=統合の意)と名付けられました。
ブローネマルク教授は基礎実験を8年、その間にインプラントの素材やデザイン、生体の反応などを徹底的に実験し、チタンが人体の拒絶反応をほとんど起こさないことを確かめ、1965年に初めて人体に応用しました。そして、1982年に世界で初めて開催されたこの方法に関する会議(トロント)で17年間に及ぶ臨床試験で培った症例とデータを公開し、驚異的な成功率で歯科界にセンセーションを巻き起こしたのです。
この治療法を日本に初めて紹介したのは、東京歯科大学補綴学第三講座に在籍していた小宮山彌太郎先生です。小宮山氏は1980年~83年までスウェーデンのブローネマルク教授のもとでインプラント治療について貪欲に学び、東京歯科大学の関根教授らとともに多くの基礎実験結果や臨床応用を国内の関連学会で発表しました。以後現在に至るまでオッセオインテグレーテッドインプラントは広く普及し、歯牙欠損に対する補綴治療として確固たる地位を築いています。
1965年、世界で初めて人体に応用されたインプラントは、上部構造の数回の作成はあったものの、この患者が亡くなる2006年まで口腔内で完璧に機能し、全く後遺症などの不快症状もなく経過したといいます。インプラント療法は術後のメンテナンスなどを通じて、歯科医師、歯科衛生士が患者さまの生涯に向き合っていく性質のものです。生体にとって異物であるチタンインプラントが感染することなく、長期間にわたって口腔内で安定して機能するためには、患者さま自身のホームケアと歯科衛生士による定期的なメンテナンスが必須です。また、かみ合わせは生涯を通じて刻々と変化し続けるものであり、その時点でベストと考えられる咬合状態を構築する必要があるため、インプラントの上部構造は十数年で1回程度は新規作成することが望ましいです。インプラント療法は、手術し上部構造を連結したらおしまいではなく、そこからメンテナンスや咬合の管理が始まり、一生にわたって歯科のスタッフと患者さまとの関係が続くのです。
当院でインプラント療法を受けた患者さまは累積で1,000名を超え、手術件数は年平均100件であり、成功率は98%を超えています。マスコミではインプラントの失敗例や訴訟などが多く取り上げられていますが、当院では、治療開始前に歯科医師によって、インプラント療法に関するリスク評価を行い安全に施行しています。
歯科口腔外科部長 田村英俊
歯科診療科のご紹介
https://medical.kameda.com/general/medi_services/index_38.html デンタルインプラントとは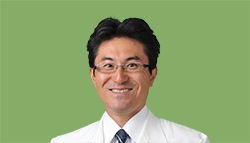
監修者
亀田総合病院歯科口腔外科 部長 / 歯科医師卒後研修室 室長 田村 英俊
【専門分野】
口腔外科全般、デンタルインプラントや顎変形症は経験が豊富。口腔顎顔面領域の外傷や口腔腫瘍も多く手掛けている。
スポーツ歯科
