- アドバンス・ケア・プランニング=将来の意思決定能力の低下に備えて、患者さまやそのご家族とケア全体の目標や具体的な治療・療養について話し合うプロセス(過程)。もしバナ≒もしものための話し合い。
前回(第4回)のコラムの中で、「ピンピンコロリ」の対義語(?)として「ネンネンコロリ(≒何らかの原因で寝たきりになって最期を迎える)」という言葉を紹介しました。今回はこの「ネンネンコロリ」の原因について考えてみたいと思います。
さてネンネンコロリの「原因」はどんなものがあるのでしょう。心不全、脳卒中、認知症、老衰、、、例を挙げればキリがありませんが、経過からこれらの原因は大きく3つのタイプに分けられると言われています。(※1)
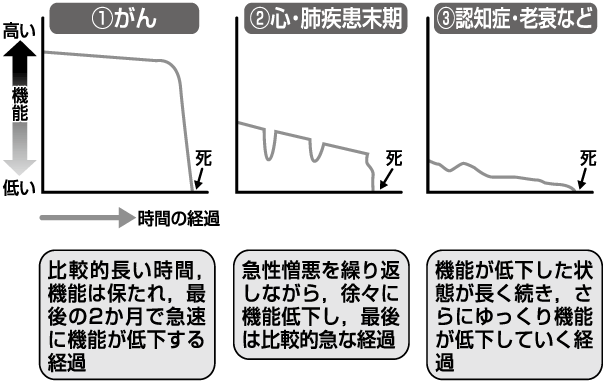
(1)がん(悪性新生物)
がんは日本人の死亡原因の第1位(約3割)とされています。この経過の特徴として、およそ亡くなる1~2ヶ月前までは身体機能が保たれます。つまり「寝たきり」の期間はおよそ1~2ヶ月ということになります。もちろん個人差はありますが、中には亡くなる数日前まで仕事や趣味の時間を過ごされる方もいます。このことから、がんの最期の経過を「ピンピンコロリ」の範疇と捉える方もいます。
(2)「心不全、呼吸不全など(臓器不全と呼ばれる一群)」
慢性心不全や慢性閉塞性肺疾患などの経過の特徴は、
- 比較的長い経過
- 時々増悪(入院)-寛解(退院)がある
- 最期も比較的“急”な経過
と言われます。グラフではところどころに“谷”のような落ち込みが見られますが、これは一時的な悪化(入院)に伴う体力低下と考えられます。徐々に身体機能が低下していく中で、「入院治療をすれば元の生活に戻れるのか」、その見通しがはっきりつかなくなってきた時が特に問題です。本人の意思、家族の思いを踏まえた治療方針の決定が望まれますが、救急室に運ばれてきた段階(時間的に切迫した状態)でこれを決定するのは容易でないことは、これまでの連載でも述べているとおりです。
(3)「衰弱・老衰」
幸いなことに(1)がんや(2)臓器不全を患わず、いわゆる「長生き」した方の経過がこれにあたると言われます。(※2)また「認知症」の経過もこれに含まれます。(1)、(2)との大きな違いとして、この(3)のグラフの横軸(時間)にはかなりの幅があり、場合によっては「寝たきり」の期間が十年以上に及ぶこともあります。(2)と同様か、それ以上に最期を迎えるまでの期間(見通し)の予測は難しく、また、本人の認知機能低下がある場合には、その都度の治療方針決定も容易ではありません。本人に意思決定能力がない場合には、本人の推定意思に沿って治療方針決定が行われるのが理想ですが、実際にそれを担う家族(≒意思決定の代理人)は大変です。(なぜなら、『ほとんどのケースで「もしバナ」がきちんとなされていないから』です。)
一口で「ネンネンコロリ」と言っても、その中身は様々です。この3つのグラフはあくまでもモデルであり、一人ひとりの病気の経過は多くの因子に左右されます。また昨今の治療や医療技術の進歩によって、これら3つの経過にも変化が生じています。(例えば、抗がん剤治療を繰り返す経過は(1)ではなくむしろ(2)に近いと言う方もいます。)
医療の進歩によって病気もある程度は予防・治療できるようになるかもしれませんが、いつかは必ず最期の日がやってきます。限りある自分の人生の最期に何を望み、どう過ごすのか。これから先、どんなに医療が進歩しても、優しくて腕の良い担当医や医療従事者(将来はロボットに代わるかもしれませんが)に出会えたとしても、一人ひとりの中にある思いを、家族や医療者と共有することの大切さは変わらないように思います。
【参考資料】
(※1) https://www.igaku-shoin.co.jp/paperDetail.do?id=PA03047_03
(※2) http://www.bmj.com/content/330/7498/1007
疼痛・緩和ケア科のご案内
https://medical.kameda.com/general/medi_services/index_47.html亀田総合病院 Advance Care Planning in AWA プロジェクト代表 蔵本浩一

